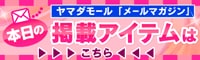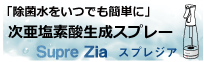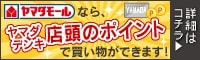コミュニティケア 訪問看護、介護・福祉施設のケアに携わる人へ Vol.24/No.11(2022-10)
商品コード:X1009784818024113
- 出版社名日本看護協会出版会
- ページ数80P 28cm
- ISBN978-4-8180-2411-3
販売価格1,540円(税込)
ポイント3%47円相当進呈
在庫お取り寄せ
株式会社ヤマダデンキ(登録番号:T2070001036729)が販売し、「株式会社トーハン」が発送いたします。
出版社コメント情報
第1特集現場での違和感に気づく 年を重ねると身体機能やコミュニケーション能力が低下し、日常生活に他者からの支援を受けざるを得なくなります。この状況は自尊心の低下を招き、それによって多くの高齢者は「助けてもらうのだから仕方がない」「我慢も必要」といった価値観を持つようになります。特に医療や介護を必要とする高齢者は尊厳が損なわれやすい、あるいは守られにくい状況にあります。本特集では、高齢者の置かれている状況を踏まえた上で、ケア提供者が抱きやすい倫理的葛藤やそれを解決する方策、倫理的葛藤をケアに生かすための組織醸成について解説します。併せて、看護職・理学療法士・介護福祉士の4人がこれまでに経験した倫理的葛藤とそれをよりよいケアに生かすための取り組みについて考察します。新型コロナウイルス感染拡大により、カンファレンスや事例検討の場は減少し、倫理的感性を高める機会は減りました。しかし、利用者本位に基づくよりよいケアを提供するには、語り合いの場は欠かせません。withコロナ時代に適した環境での語り合いをそろそろ再開してはいかがでしょうか。 第2特集「持てる力」を高める支援 在宅療養の場では、療養者の困り事に寄り添いながら「持てる力」を生かす支援が求められます。しかし、持てる力は目に見えてわかりやすいものばかりでなく、看護師をはじめ周囲の人たちの認識・かかわり方などによって引き出されるものもあります。このような力を高める支援には、対象者への固定観念を排し、本人の顕在的・潜在的なニードに気づき、その充足にはどのようなケアが必要であるかを導き出すことが求められます。高齢であっても、疾患や障害を有していても、その人の持てる力を見極めて援助の方法を探ることは、看護において欠くことのできない視点といえるでしょう。本特集では、「持てる力」とは何か、それを高める働きかけとはどうあるべきかについて論じた上で、療養者の「意欲・意思表示の力」「生活上の機能」「対人関係力」に焦点を当て、よりよく生きるための支援の実際を紹介します。